 |
 |
 |
 |
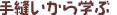

●針の発達
原始時代には、石や骨で作られたキリ状の針で皮や布に穴をあけ、そこに紐を通して、綴じ合わせていました。
これは、すき間もでき、手間もかかるので不便でした。
16世紀ごろから、手縫いをお手本にして、縫う機械の研究が盛んにされるようになりました。 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |


1589年に英国のウイリアム・リーが妻の毛糸を編むのをみて、機械編みを考えたのが、ミシンの研究の始まりです。
1790年にイギリスのトーマス・セントにより、ミシンの条件を備えた機械が発明されました。
1844年に米国人は本縫いミシンの組立に成功し特許を取りました。
同じ頃にアイザック・シンガーは、修理にきたミシンを詳しく調べ、改良して現在の本縫いミシンの基になるミシンを開発しました。
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
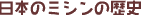

| 1854年(安政元年) |
 |
黒船2度目の来航時、幕府への献上品の中にミシンがありました。 |
| 1860年(万延元年) |
 |
遣米使節の通訳中浜万次郎(ジョン万次郎)が土産として、持ち帰りました。 |
| 1881年(明治14年) |
 |
東京で開かれた第2回内国勧業博覧会に国産ミシン第1号が展示されました。 |
| 1924年(大正13年) |
 |
国産の本縫いミシン(パイン)の製造が開始されました。 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
|